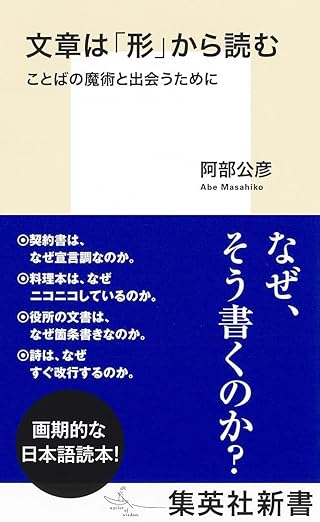

そんな声に押され、国語教育の大改造が始まった。
文科省が重視したのは実用性。
文学はこの枠には入らないという。
しかし、この考え方は正しいのか?
文章を読む際に大事なのはことばの「形」を見極める力だと著者は言う。
そこを鍛えるトレーニングをしたい。
その助けになるのが文学作品を読む技術なのだ。
本書では契約書、料理本のレシピ、広告、ワクチン接種の注意書き、小説、詩など幅広い実例を用いて「形」を読む方法を指南する。
それは、生成AIが生み出す「文章」と渡り合う際にも格好の助けになるだろう。
画期的な日本語読本の誕生!
【目次】
第1章 学習指導要領を読む
第2章 料理本を読む
第3章 広告を読む
第4章 断片を読む
第5章 注意書きを読む
第6章 挨拶を読む
第7章 契約書を読む(1)
第8章 契約書を読む(2)
第9章 小説を読む
第10章 詩を読む
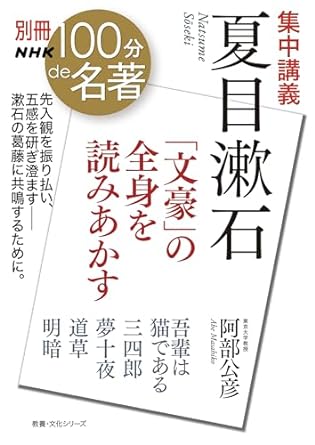
漱石の心身の「葛藤」に刮目し、読者の共鳴を誘う、鮮烈な集中講義全5講。
そのデビュー作から絶筆までを五感を駆使して「読み証し」「読み明かす」。2019年3月「夏目漱石スペシャル」に大幅に加筆。
【目次】
はじめに─夏目漱石と「出会う」ために
第1講『吾輩は猫である』の「胃弱」
第2講『三四郎』と歩行のゆくえ
第3講『夢十夜』と不安な眼
第4講『道草』とお腹の具合
第5講『明暗』の「奥」にあるもの
あとがき
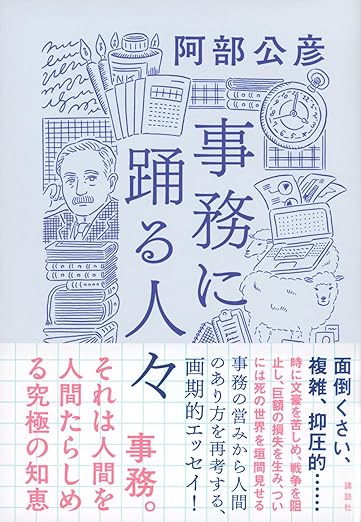
面倒くさい、複雑、抑圧的……
時に文豪を苦しめ、戦争を阻止し、巨額の損失を生み、
ついには死の世界を垣間見せる。
「事務」
それは人間を人間たらしめる究極の知恵。
事務の営みから人間のあり方を再考する、画期的エッセイ!
クソどうでもいいのに倒錯的な愛をかきたてる
かくも人間くさい事務の世界への探究。
第1章 漱石と大日本事務帝国
第2章 事務の七つの顔
第3章 事務処理時代の「注意の規範」
第4章 『ガリヴァー旅行記』の情報処理能力
第5章 「失敗」から考える事務処理
第6章 身体儀式と事務の魔宮
第7章 事務を呪うディケンズ
第8章 鉄道的なる事務
第9章 エクセル思考で小説を書く
第10章 事務の「感情」を考える
第11章 事務に敗れた三島由紀夫
第12章 事務と愛とバートルビー

二一世紀に読み継ぐべき文学をポケットに入れて――。第一次世界大戦直前から現代まで一〇〇年の海外文学六〇冊、日本文学四〇冊を、文庫で読めるものに限り厳選。現代文学の最前線に立つ作家、翻訳家、文学者ら五三名が愛の記憶、歴史と社会、生命のきらめき、想像力の冒険のジャンルごとに解説する。来たるべき“世界文学全集”の提案。
"
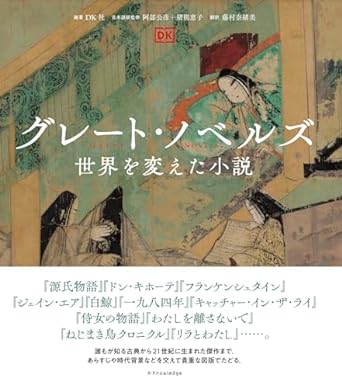
古今東西の傑作小説を豊富なビジュアルで紹介!
『源氏物語』『ドン・キホーテ』『フランケンシュタイン』『ジェイン・エア』『白鯨』 『一九八四年』『キャッチャー・イン・ザ・ライ』『侍女の物語』『わたしを離さないで』『ねじまき鳥クロニクル』『リラとわたし』……。
誰もが知る古典から21世紀に生まれた傑作まで、
あらすじや時代背景を交えて貴重な図版でたどる。
目次(抜粋)
第1章 1800年まで
源氏物語/西遊記/ドン・キホーテ/ロビンソン・クルーソー/危険な関係
第2章 1800~1870年
高慢と偏見/フランケンシュタイン/ジェイン・エア/嵐が丘/白鯨/ボヴァリー夫人/大いなる遺産/罪と罰
第3章 1870~1920年
アンナ・カレーニナ/ある婦人の肖像/ハックルベリー・フィンの冒険/ブッデンブローク家の人びと/スワン家のほうへ
第4章 1920~1950年
ユリシーズ/グレート・ギャツビー/審判/灯台へ/異邦人/雪国/一九八四年
第5章 1950~1980年
キャッチャー・イン・ザ・ライ/山にのぼりて告げよ/山猫/ブリキの太鼓/アラバマ物語/イワン・デニーソヴィチの一日/個人的な体験/百年の孤独/巨匠とマルガリータ
第6章 1980年~現在
真夜中の子供たち/精霊たちの家/侍女の物語/ビラヴド/赤い高粱/ねじまき鳥クロニクル/わたしを離さないで/半分のぼった黄色い太陽/リラとわたし
"
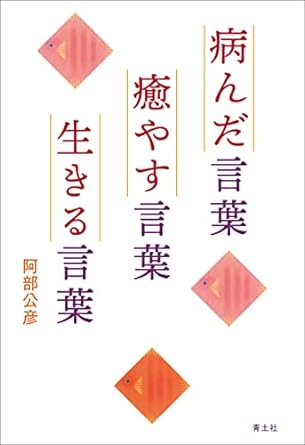
読めば「言葉」が好きになる。
「言葉を甘く見てはいけない。言葉や人間をめぐる学問の最大の効用は、世界を知り尽くしてやっつけることにあるのではありません。むしろ世界の不思議さに驚き、日々新しい畏怖の念にかられること、それが先につながります。今、私たちに必要なのは、まずは驚く力なのかもしれません」(本書内「言葉は技能なのか」より)。言葉を読むとは何か。言葉を使うとは何か。言葉を学ぶとは何か。そして、言葉を守るとは何か。英文学教授が、文学作品から言語教育まで、渾身の力を込めて綴ったエッセイ・評論集。

フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、ポー、村上春樹――
「黄金の抜粋」で出会う本物の英語!
カンタンな英文だけでは、英語を操るための「体幹」が身につきません。
歯ごたえたっぷりの名作には、英語的感覚を身につけるためのお役立ちヒントがたっぷり。
時代背景や小説のルールなど丁寧に解説し、和訳、語注や文法の説明も充実。読むための入り口までご案内します。昔から気になっていたけど、なかなか手に取れなかったという有名作品の原文をこの機会に是非。
読んでみると、やっぱりおもしろい! おかしい! 怖い!
おもしろくて読む英語は、次のステップにつながります。読まずにいるのはもったいない。
東京大学英文学教授による、英米文学講義。

ここから始まる小説を読むという愉しみ
読売新聞の読書面「本よみうり堂」で紹介された約30年分の名著60冊を1冊で網羅。
あなたは何冊読んだことがありますか

6人の慧眼が選ぶ必読の「名場面」集!
【全作解説つき】
ネタバレ御免!
1作10分、贅沢な文学体験
芥川龍之介 三島由紀夫 川端康成
夏目漱石 武田麟太郎 梶井基次郎
谷崎潤一郎 村上春樹 永井荷風
向田邦子 樋口一葉 田山花袋
――などなど、日本文学の代表60作を網羅!

すべては「聞く」からはじまる――日本語話者のための英語習得法
「英語は聞きとりになるとさっぱり…」「英語学習,どこから始めればいい?」――そんな方は,英語の運動感覚を身につけよう! 聞く」を通して,英語の基礎力を鍛えるための考え方や練習法を解説.単なる「実用英語」に終わらず,現実のコミュニケーションの土台となる気分,態度,思惑などの「人間的要素」までを重視する.語学の本来の意義も考える一冊

一連の「国語」改革は何が問題なのか?
東大文学部の教授陣による、緊急講演録

「日本近代文学史上に燦然と輝く大作家・夏目漱石。彼の作品は、ありがたく押し頂いて読まなければいけないのか?それとも――。
気鋭の英文学者が『三四郎』『夢十夜』『道草』『明暗』の4作品を取り上げ、B級グルメのように作品を味わうことを提案。漱石作品の新たな魅力に光を当てる。」

「大学入試の英語が4技能! 」とのニュースがメディアに流れた。しかし、多くの人は「え、4技能?」「どこがあたらしいの?」と思ったことだろう。それもそのはずで、この「4技能」看板は実態のないブラックホールのようなものである……迷走する日本の教育行政を検証し、教育の暗黒時代から身を守るための方法を模索する。

文豪の冒頭部への「らくがき」から、すべてを読み解く。

あの名作はどのようにして生まれたのか? 文豪たちの創作活動とその現場を辿る。

「幼さ」が自ら声を持って語るとき、独特の魔力をたたえた不思議な磁場が生まれる。太宰治『人間失格』、村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』から谷川俊太郎、武田百合子、ルイス・キャロルまで、「幼さ」特有の心理、美学、思想の潜在力をさぐる。

ヨーロッパ近代は「礼節」の時代だった。文学作品の語り手も、読者や登場人物に対し、愛や配慮や善意をたっぷり示す。が、その裏には悪意や不機嫌、嫌悪も垣間見える。「善意の政治学」を軸に、英・米・アイルランドの近現代文学を大胆に読み直した、独創的で味わい深い一冊。

物語に描かれた50の食事シーンが今よみがえる――読書家も、くいしんぼうも、写真ファンも大満足

少し斜めから見る 英語の仕掛け。
小説・批評・英訳聖書などのさまざまな素材を使って、英語の文章の技について解き明かすエッセイ集。さらに、英語の名言を解説したコラムも併録

ちょっといい感じ♪…だけが詩ではない。
名前をつける、数え上げる、黙る、恥じる。日常の行為にはあれこれ詩のタネが隠れている。萩原朔太郎から谷川俊太郎まで、教科書のあの詩人の作品がもっとおもしろく読める。

「それを教えることはできません」 聖職者(ラビ)を目指して勉強中の青年が頼るうらぶれた結婚仲介業者は,青年が目にとめた写真の女性にだけは合わせてくれない.この女は何なのか……? ニューヨーク下町のユダヤ人,暗い現実に光が差し込む表題作ほか,イタリアでの新旧世界のギャップを描いた「湖の令嬢」など,現代のおとぎ話十三篇.

近代は凝視の時代。詩が散文に取って代わられるプロセスにも凝視がからんでいた。美術、文学、政治、フラクタルなどにも話題を広げながら、凝視、注意散漫、陶酔、スローモーションといったさまざまな目の動きを読み解く。サントリー学芸賞受賞。

小説の読み方にはコツある。漱石、太宰、志賀から、絲山秋子、佐伯一麦、古井由吉、吉本ばななまで、「気になる部分」に注目することで見えてくる現代日本小説のほんとうの姿。

英語ならではの快楽とは?味わいとは? 英米文学の名品の細部をひと味ちがう角度から読み直し、英語ならではの感触を説明しながら小説の読み方を提案する。手軽な英米文学入門。

スローモーションはなぜうら悲しいのか? その効用は? その背後にある思想は? 「ゆっくり」の神話を解体し、近現代における視線とスピードの関係を考える。



